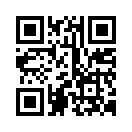2007年06月18日
夏の始まりにはナーベーラーンブシーを食べよう

6月といえば本土では梅雨入りシーズンだが、沖縄では梅雨が明けて本格的な夏の始まりである。梅雨のことをウチナー口(沖縄語)では「スーマンボースー」といい、その意味は1年を24節気に分けた季節の区分の中の「小満」と「芒種」から来ている。スーマンボースー(小満芒種)の時期は、本土が移動性高気圧に覆われて、さわやかな五月晴れが広がるのに対し、移動性高気圧のヘリに当たる沖縄県地方は、東西に延びた前線と南からの湿った風の影響で雨の日が続く季節になるのである。
 ただ、上空の前線への湿った風の流入は間欠的なので、沖縄では梅雨入りしても雨はしとしと降ることはなく、「降るときは降る、降らないときは降らない」と大雨と晴れてはいるが湿度の高い日が交互にやってくるのが、沖縄の梅雨の中盤までの特徴といえる。そして梅雨前線が本格的に活動してくる6月中旬ごろになると雨は最盛期を迎え雨量は増えるのであるが、今度は太平洋高気圧が張り出してくるため、しとしと雨を降らす梅雨前線は北上してしまい、沖縄では長雨のないまま梅雨は終わるのである。ちなみに太平洋高気圧が張り出すころに吹く風を「カーチーベー」といい、漢字で書くと「夏至南風」となる。沖縄では「夏至」の前後から吹き出す「カーチーベー」が梅雨を追い払い、本格的な暑さが始まるともいわれているのである。
ただ、上空の前線への湿った風の流入は間欠的なので、沖縄では梅雨入りしても雨はしとしと降ることはなく、「降るときは降る、降らないときは降らない」と大雨と晴れてはいるが湿度の高い日が交互にやってくるのが、沖縄の梅雨の中盤までの特徴といえる。そして梅雨前線が本格的に活動してくる6月中旬ごろになると雨は最盛期を迎え雨量は増えるのであるが、今度は太平洋高気圧が張り出してくるため、しとしと雨を降らす梅雨前線は北上してしまい、沖縄では長雨のないまま梅雨は終わるのである。ちなみに太平洋高気圧が張り出すころに吹く風を「カーチーベー」といい、漢字で書くと「夏至南風」となる。沖縄では「夏至」の前後から吹き出す「カーチーベー」が梅雨を追い払い、本格的な暑さが始まるともいわれているのである。ところで梅雨が明けるといえば、沖縄では「ハーリー鉦が響くと梅雨が明ける」ともいわれている。今年、ハーリーが行われる旧暦5月4日は6月18日。例年の梅雨明けが6月23日といわれているので、「ハーリー鉦が……」というのはあながち間違いではない。
さて、ここからが本題ね。
毎月、沖縄の年中行事とそれに関する食べ物を紹介するこのコーナーだけど、今月の大きな行事はハーリーしかない。が、ハーリーと「ユッカヌヒー」に食べるポーポーやチンビンの話は先月書いたので、残る6月(旧暦5月)の行事は29日の「5月ウマチー(旧暦5月15日)」しかない。「5月ウマチー」は豊作を祈願する稲穂祭りで、ミキと呼ばれるお粥を醗酵させた飲み物や、泡盛、ウサチ(酢の物や和え物のこと)を祖霊に供えた。
で、今回、このコーナーで紹介する伝統料理がミキや泡盛、ウサチだけではあまりにも淋しいので、夏の始まりに出回る旬の野菜とその食べ方を紹介しよう。

沖縄を代表する夏の野菜といえば、今や全国区となったゴーヤーがあげられるが、沖縄では重要な夏の野菜として、ゴーヤーに負けず劣らず愛され食べられているのが「ナーベーラー」である。「ナーベーラー」とはヘチマのことで、夏になると夏バテ防止として、あるいは暑さに負けた体に優しい料理として「ナーベーラーンブシー」を食べているのである。ちなみにンブシーとは、

汁気の多い野菜を使い豆腐と茹で豚肉と一緒に蒸し煮にして、味噌で味を調えた、チャンプルーと並ぶ沖縄家庭料理の一つでもある。
作り方は皮をむいたナーベーラーを厚めに切り軽く炒めて、豆腐と短冊に切った茹で豚肉(またはポークランチョンミート)を入れ、蓋をして蒸し煮にすると、ナーベーラーからドゥージル(ヘチマからでた水分)が出る。そこに味噌を加えるとンブシーが出来上がるのである。
 ナーベーラーには炭水化物やビタミンC、ミネラルと微かな糖分を含んでいるので、味噌との相性もよく、わりと上品な味わいが疲れた胃袋を優しくいたわるのである。
ナーベーラーには炭水化物やビタミンC、ミネラルと微かな糖分を含んでいるので、味噌との相性もよく、わりと上品な味わいが疲れた胃袋を優しくいたわるのである。梅雨が明けて本格的な夏が始まる少し前から市場にはナーベーラーが出回る。
「ハーリー」や「5月ウマチー」など、これからの沖縄の年中行事は夏の炎天下で行われることが多い。そんな時ウチナーンチュは今が旬のナーベーラーンブシーを食べて、夏負けしないよう体力をつけて行事を行うのであった(たぶん)。
あ、ところで、ナーベーラーンブシーを作る要領で、味噌の代わりに市販のカレールウを入れると美味しいナーベーラーカレーもできるよ。作り方もチョー簡単で短時間ですむので、年中行事でどこかに出掛けなければいけないときなどナーベーラーカレーはおすすめだよ。

筆者プロフィール:嘉手川 学(かでかわまなぶ)
フリーライター、沖縄県那覇市生まれ。沖縄のタウン誌の草分け『月刊おきなわJOHO』の創刊メンバーとして参画。沖縄ネタならなんでもOKで特に食べ物関係に強い。現在も『月刊おきなわJOHO』で食べ物コーナーを15年以上掲載中。
著書、編著、共著に『沖縄大衆食堂』、『笑う沖縄ごはん』、『泡盛『通』飲読本』(各双葉社)など多数ある。今年になって共著で3月に『沖縄離島のナ・ン・ダ』(双葉文庫)と『もっと好きになっちゃった沖縄』(双葉社)、5月には『沖縄食堂』(生活情報センター)が発売。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。