2010年02月01日
『琉球語の美しさ』仲宗根政善著

ある大学で半年ごとに4回、講義を行っている。誰が? 僕がである。まぁ、とは言ってもかなり変則的な授業でありまして、数十名の生徒を相手に、沖縄県産本のことを宣伝するような内容である。そして最終的には「もしあなたが沖縄県産本を企画するとしたら」というレポートを提出してもらっている。つまり日頃仕事でやっていることとそんな変わらないというわけだ。
クイズはこんな感じ。
Q:以下は、沖縄出身の著者とその作品です。名前の読み方を書いて、その作品と結んでみましょう。
池上永一 ( )・ ・『琉球の時代』
船越義彰 ( )・ ・『ひめゆりの塔をめぐる人々の手記 』
高良倉吉 ( )・ ・『うちあたいの日々』
仲宗根政善( )・ ・『きじむなぁ物語』
新城和博 ( )・ ・『バガージマヌパナス』
いかがだろうか。サービス問題だが、パーフェクトは残念ながらいなかった。この連載ではおなじみの人たちだ。セレクトしたポイントは特にないのだが、なぜかしら沖縄の本というと僕の心にひっかかる著者たちなのである。
 さて話はがらりと変わりまして、数日後、ふと事務所の本棚を見ていたら、仲宗根政善氏の『琉球語の美しさ』が目にとまった。方言学者として故郷の言葉をまとめた大著『沖縄今帰仁方言辞典』や、沖縄戦で教師として女子生徒らを引率した際の痛ましい体験を生徒らの手記とともにまとめた『ひめゆりの塔をめぐる人々の手記』などがよく知られている。でも僕にとって1995年2月に亡くなった氏の遺稿集ともいえる『琉球語の美しさ』は、なぜかしらいつも心の片隅にある不思議な存在の一冊なのだ。沖縄の言葉の断片を、深い知識と深い郷土愛に満ちた文章でつづった、珠玉の一冊。版元は古書店にしてかつて沖縄県産本の版元でもあった「ロマン書房」で、亡くなった年の七月に発行している。
さて話はがらりと変わりまして、数日後、ふと事務所の本棚を見ていたら、仲宗根政善氏の『琉球語の美しさ』が目にとまった。方言学者として故郷の言葉をまとめた大著『沖縄今帰仁方言辞典』や、沖縄戦で教師として女子生徒らを引率した際の痛ましい体験を生徒らの手記とともにまとめた『ひめゆりの塔をめぐる人々の手記』などがよく知られている。でも僕にとって1995年2月に亡くなった氏の遺稿集ともいえる『琉球語の美しさ』は、なぜかしらいつも心の片隅にある不思議な存在の一冊なのだ。沖縄の言葉の断片を、深い知識と深い郷土愛に満ちた文章でつづった、珠玉の一冊。版元は古書店にしてかつて沖縄県産本の版元でもあった「ロマン書房」で、亡くなった年の七月に発行している。〈単語を集めている。それはいわば沖縄の民衆の生活をのぞく無数の節穴である。私はただその節穴をあけているにすぎない。その節穴をあけなければ全く民衆の生活は見えないのである。と同時にのぞかなければ民衆の生活は自然には見えない。小さくてもよいからのぞき穴をあけておくことは必要なのだ〉
(「序に変えて」より 以下引用はすべて同じ)
無数の節穴は、氏の手によって夜空に輝く無数の星のように見える。見上げる人がいることによってその美しさを知ることができるのだろう。主にノートに記されていた短文なのだが、一つひとつの響きが深いのだ。愛があり諧謔があり知識がある。
母親が亡くなった日に、母の伯母に言われた言葉「マーマー クーヤ ワヌー ヌゲーラ ちルーヌ ちマールンネー スン」。直訳では「姉さん 今日は 私 どうしてかしら 血管が ちぢまるような気がする」。しかし直訳ではこの言葉の持つ意味はまったく伝わらないであろうと氏は語る。
〈……これは、誰の声でもなく母だけが持っている声であったのである。私の母が地球上に発した一度の最後の声であったし、ことばであった。ことばを厳密に同じように二度発することは、人間世界ではありえない。たった一度だけ、発しては消え消えては発してゆくのが、人間のことばである。(中略)方言はそれを用いる人々に無限の深さを伝えながらたえず消えて行く。〉

言葉はたえず消えていく。落葉のように森の奥深く積もり朽ち果てていく。しかし言葉の収集、方言を知るということは、ただ枯れ葉を集めているのでない。わずかに実存しているものをたよりに、新しい言葉からもかつて消え去ったもののいきさきがわかり、それは深い生命感に通じるものだと氏は言う。
〈新しい語といえども一度しか存在しなかったものであり、一回一回その度に滅亡してしまったものである。それを観察した時は古いことばも新しいことばももうなくなるのではあるまいか。〉
僕がこの本の事がいつも心の片隅にあるのは、きっとこの言葉のせいだ。沖縄で、こんな本を作っていきたいと、かつての僕は願っていたに違いない。
次回から学生にクイズを出すときは、隠れた名著、珠玉の一冊である『琉球語の美しさ』を挙げることしよう。
●新城和博の『ryuQ100冊』バックナンバー:
http://ryuq100.ti-da.net/c73391.html

プロフィール:新城和博(しんじょうかずひろ)
沖縄県産本編集者。1963年生まれ、那覇出身。編集者として沖縄の出版社ボーダーインクに勤務しつつ、沖縄関係のコラムをもろもろ執筆。著者に「うっちん党宣言」「道ゆらり」(ボーダーインク刊)など。
ボーダーインクHP:http://www.borderink.com/
カテゴリー
最新記事
過去記事
最近のコメント
mikosan / 『沖縄の神社』(加治順人著)
愛樹 / 本当は教えたくない絶品B級・・・
万民の天☆金正子 / アメリカで描かれた小さな「・・・
たーちゅのはは / パパイヤをシリシリーしてパ・・・
ハッシー / 厳選・沖縄音楽(9月号)「白・・・
お気に入り
ブログ内検索
QRコード
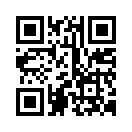
読者登録
プロフィール
ryuQ編集室
















